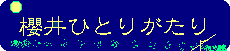「褐色の肌」
美沙は、滑らかな褐色の肌の持ち主だった。夏も冬もその色は変わらない。「日焼けサロンに通ってるの」と誰かに訊かれても、にこりと笑ってごまかしてしまう。
そんな彼女の肌に、雄哉は夢中ですがりつく。挿入はしない。ひたすら身体を擦り合わせるだけだ。
射精の瞬間が近づくと雄哉はきまって
「このままでいい?」と美沙に訊く。
「うん」と答えた美沙の手が伸びて、彼の頭を抱き寄せる。するともう雄哉には、褐色のうねりを漂う乳首の他に何も視ることを許されない。その眺めこそ彼の生きる世界のすべてに思えてくる。雄哉の肩がぶるっと震える。生ぬるい体液が美沙の太腿に流れ出す。
雄哉の息づかいが鎮まると、美沙がおもむろに自慰をはじめる。彼女の腰が浮き上がる頃を見計らい、雄哉がその右肘をとらえる。
「してあげよう」
新芽のように尖ったものを彼の中指がみつける。その硬さと、美沙の洩らす喘ぎの深さで、そんなに時間がかからないことが知れる。
「また週末に会えるかな」
「来週は無理かも……あっ、しばらくはだめ」
「本命のオトコができたんだろ」
冗談めかして雄哉が言うと、美沙は無言で微笑んだ。肌の色を訊かれた時と同じ笑顔だった。雄哉は自分の言葉が当たっていたことを直感した。
*
雄哉には律子という婚約者がいる。友人の紹介をきっかけに付き合い出し、もう二年になる。名門女子大出のお嬢様だが、それを鼻にかけた様子もないのが気にいった。
セックスもしおらしく受身一辺倒だ。だが雄哉自身、いまさら激しい性に飢える齢でもない。三十路目前の男女にふさわしい静かな恋愛に、彼は満足しきっていた。
その静けさをやぶったのが、三ヶ月前、彼の職場にアルバイトとして入った美沙だった。いま流行りのフリーターで歳は十九という。
軽くお愛想のつもりで誘ったら、すんなり飲みについてきた。酔った勢いでホテル街に足を向けても、つないだ手をほどかない。「時間は?」と訊ねたら、「いつまでもいいよ」と答えたので、思い切って空室の表示が灯る門をくぐった。その時を境に、雄哉はめくるめく褐色の世界に足を踏み入れた。
水曜日の仕事を終えた後、雄哉は美沙を喫茶店に呼び出した。
二人の飲み物が運ばれた。フレッシュを半分ほど入れてスプーンでかき混ぜると、雄哉はひとくちコーヒーを啜った。それからまっすぐ顔を上げ「どんな男なんだ」と問いかけた。
オレンジジュースのストローに口をつけ、美沙は上目づかいに彼を見た。
「オマエの彼氏のことを聞いてるんだよ」
さらに雄哉が突っ込むと、美沙は下を向いたままの唇で
「ハタチの大学生」とつぶやいた。
「やったのか、そいつと?」
美沙は例のあいまいな微笑みを返した。雄哉はあきらめたような気持ちになって、ミルクピッチャーを手にした。
「まあ、若い者同士で仲良くやるんだな」
彼は、ピッチャーの中身をカップに注ぎきった。どんよりと白い膜が、褐色の液面を覆った。
店を出て裏通りを歩いた。ふと横目で見た路地の奥、けばけばしい電飾看板の灯が雄哉の胸に熱いものを注いだ。彼は美沙の肘をとって進路を変えた。
「なによ、どうしちゃったの」
雄哉は黙々と突き進む。耳元に聴く息の荒さと、行く手に見える看板の文字から、美沙はたちまち彼の欲望を察した。
「やだ、やめてよ」
彼女は腰を引き、雄哉の手を振り払おうとする。
「どうしてダメなんだ。若い男ができたら、もうオレにはやらせないのか」
「そうじゃないけど、こんなのイヤなの」
「どこがイヤなんだ、え?」
「だって雄ちゃん、普通じゃないんだもん……やり方が……」
雄哉の眼の中で背景の街が崩れはじめた。すべて跡形もない闇の中で、爛々ときらめく瞳が、今にも泣き出しそうな彼の顔を見据えていた。
雄哉は、律子を相手にやりきれぬ想いを満たそうと考えた。だが電話口の婚約者はこう答えた。
「それがね、なかなか連絡くれないから土日の予定を入れちゃったの」
「三日も先の話じゃないか。今から断れよ」
「だめよ。友達との約束ならいいけど、お稽古ごとのお師匠さんがからんでるもの」
「じゃ、いいよ」と吐き捨てて、雄哉は電話を切った。茶会か、書の展覧会か、どちらにせよ金持ちの道楽だろう。聞けばむかつくのが関の山だ。
グラスに半分ウイスキーを注いだ。冷蔵庫の氷を取ろうとキッチンに立ったら、むらむらと怒りがこみあげてきた。
「くそっ」と短く叫んで、彼はグラスを床に叩き付けた。足元に濡れた破片が散らばった。その琥珀色のきらめきさえも、美沙の瞳を思い出させた。彼はスリッパの底でひときわ光るかけらを踏みにじった。
* *
翌日、雄哉は風邪を理由に会社を休んだ。しんじつ体調が悪い訳ではないが、ずっと目を開けたまま布団の中にいた。
ようやく昼過ぎに床を離れた。牛乳とパンで食事をすませ、着替えをしてアパートの部屋を出た。
雄哉の会社は、駅西の賃貸ビルの中にある。そのビルの玄関を見張ることができる位置に、彼は車を停めた。
美沙は一時間ほどで現われた。今日は伝票集計の翌日、予想通り早あがりだ。雄哉は急いで車を降りて彼女に走りよった。
「あれ雄ちゃん、風邪で休みじゃなかったの」と驚く美沙の手を掴まえ、強引に車まで引っ張った。
「痛い、痛い」と叫んでも、雄哉は聞こえない振りをした。彼はドアを開け、彼女の背中を突き押した。美沙は前のめりになって助手席に転がり込んだ。
車は、外環状から高速のインターチェンジへと入った。ランプウェイに差しかかった時、雄哉がはじめて口をきいた。
「ケータイ持ってるか」
「うん」と、美沙はハンドバッグを開いた。
「ちょっと貸してくれ」
雄哉は運転席の窓を開いて、美沙から受け取った携帯電話を車外に放り投げた。
「なにすんのよ」
答えず彼はアクセルを踏み込む。
「なんであんなことするの。ねえ、ちゃんと弁償してよ」
「うるさい、黙ってろ」と、雄哉は美沙を怒鳴りつけた。その剣幕に怖れをなし、美沙は口をつぐんだ。
すっかり日が暮れた。車はまだ高速を走っていた。フロントガラスにぽつぽつと雨粒がかかりはじめた。カーラジオが台風の接近を告げている。降り止みを繰り返すたび雨風の勢いは強まり、一台前の車を見ることさえままならなくなってきた。次のインターが近づくと、都合よくホテルのネオンが見えたので、そこで高速を降りることにした。
ベッドの端に二人は腰掛けた。裸にバスタオルを巻いた美沙が、雄哉に話しかけた。
「こんなに遠くまできちゃって、会社はどうすんの」
「もう、会社へは行かなくていい」
「そんなことしたら、二人ともクビになるわよ。お金にこまるじゃない」
「だいじょうぶだ」雄哉は、抱きしめた美沙の身体に自分の重みをあずけた。
「金ならオレが持っている。美沙はもうバイトしなくていい」
「そんならケータイも弁償してくれる」
「もちろん、最新機種で」と言って、雄哉は彼女と唇を合わせた。
* * *
海浜公園の駐車場に車を停めた。台風の上陸が近いせいか、ほかの車は見当たらない。
「これでも歩くの」と美沙がぐずる。
「ああ」と答えて雄哉は車を降りる。助手席側にまわって彼女を促す。さしかけられた傘の下に美沙はしぶしぶ潜り込む。
堤防の道を二人は歩く。強風に骨を折られ、傘はすぐに捨ててしまった。こうなると、美沙もずぶ濡れの散歩を楽しむ気になってきた。
比較的、波がおとなしい場所を選んで砂浜へと降りた。それでも近くの消波ブロックが、高々と飛沫を噴きあげている。
「すごいねえ、海の色が」と美沙が言う。
たしかに二人の知らない海の色だった。波が砂や泥を捲き、海水は一面ミルクコーヒーのように濁っている。ただ、波がしらだけがまぶしく白い。
「なんかおいしそう。飲んでみたい」と美沙が喜ぶ一方で、雄哉はしだいに蒼ざめていく。わななく彼の唇に気付いて美沙が訊ねた。
「どうしたの雄ちゃん、寒いの」
「いや」と顔を背けてから、「オマエ、もう行っていいよ」と雄哉は言い足した。
「行くってどこに」
「どこへでも行っていい。なんならオレの車を使え」と、雄哉は車の鍵を渡す。
「そんな、ひとりじゃイヤよ」
「だったら車で待ってろ。頼むから、オレの側にいないでくれ」
戸惑いながらも、美沙はしょんぼりと堤防の階段をのぼっていく。
ときに海は、いのちの揺りかごと言われる。けれどいま雄哉は、海を死の入り口として眺めていた。さらに、そのうねりに美沙の肌を視て、その轟きに美沙の喘ぎを聴いていた。生きて帰れぬことは解っていても、寄せくる波に躍り込んでいきたかった。雄哉はかろうじてその衝動に耐えた。そして、浜の高いところに曳き上げてある小舟に向かい歩いていった。
舷に身を寄せ、彼はズボンの前を開いた。いつの間にか硬くなった性器をつかみ出し、強く速くこすり始めた。さしたる快楽もなく、精液が横なぐりの風にはじけて飛んだ。
短い興奮がさめると、雄哉はその場に跪いた。濡れ砂を両手で掻きながら、「やっぱりだめだ」と繰り返した。
すると、その瞬間を待っていたかのように、誰かが彼の肩をたたいた。
振り向くと美沙がいた。彼女は彼の前にしゃがみこみ、褐色の顔をほころばせた。
「さっきから見てたよ。雄ちゃん、よっぽどつらかったんだね」
横ざまにはげしく、黄色い髪がなびいていた。
いまさら恥ずかしさはなかった。深く美沙の胸に顔をうずめた。とりあえずほっとする一方で、「よしよし」と背中をさする手の心地よさに、彼は懼れを抱かざるをえなかった。
了
|